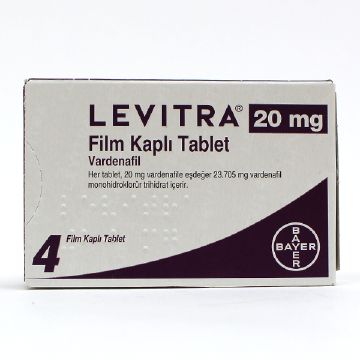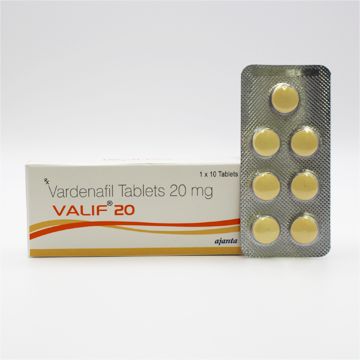抗血小板薬
- 主な抗血小板薬とその効果
-
抗血小板薬は、血小板の凝集を抑制することで血栓形成を予防する薬です。
動脈血栓症の予防や治療に用いられ、脳梗塞や心筋梗塞などの重大な心血管リスクを低減します。医師にアンケートを取った結果では、抗血小板薬として処方することが最も多いのは、アスピリンだとわかりました。
2位のクロピドグレル(商品名:プラビックスなど)と大差がつき、3位はシロスタゾール(商品名プレタールなど)でした。アスピリンは血小板凝集を抑制する効果があり、脳梗塞や心筋梗塞の再発予防、冠動脈バイパス術後の血栓予防などに用いられます。
クロピドグレルも血小板凝集を抑制し、虚血性脳血管障害(心原性脳塞栓症を除く)後の再発抑制、急性冠症候群などに使われます。シロスタゾールは血小板凝集抑制と血管拡張作用を持つ薬で、慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍、疼痛および冷感などの虚血性諸症状の改善、脳梗塞(心原性脳塞栓症を除く)後の再発抑制などに処方されることがあります。
- 抗血小板薬の使用上の注意点
-
抗血小板薬を処方されたら、服用後には以下の副作用に注意しましょう。
-
出血リスク
最も重要な副作用は出血です。
特に消化管出血や頭蓋内出血に注意が必要です。 -
併用薬との相互作用
他の抗血栓薬(抗凝固薬など)との併用時は出血リスクが増加するため、慎重な管理が必要です。 -
耐性
特にアスピリンやクロピドグレルで報告されており、効果不十分となる可能性があります。 -
手術・処置時の休薬
出血リスクを考慮し、適切な休薬期間の設定が必要です。
-
- 抗血小板薬の利点と注意点
-
抗血小板薬は、心筋梗塞や脳梗塞などの動脈血栓症の一次予防・二次予防において重要な役割を果たしています。
特に、冠動脈疾患や脳血管疾患の既往がある患者では、長期的な抗血小板療法が推奨されています。一方で、抗血小板薬の使用には常に出血リスクとのバランスを考慮する必要があります。
特に高齢者や腎機能障害患者では、個々の患者の特性に応じた慎重な薬剤選択と用量調整が重要になってきます。抗血小板薬の選択は、患者の病態、リスク因子、併存疾患、出血リスクなどを総合的に評価して行います。
また、薬剤の特性(作用発現時間、効果持続時間、代謝経路など)も考慮に入れる必要があります。抗血小板薬は、正しく使用することで心血管イベントのリスクを大幅に低減し、患者の予後を改善する重要な薬です。
生涯にわたって服用し続ける方も少なくはないため、定期的に薬と自分の体との相性を確かめていきましょう。