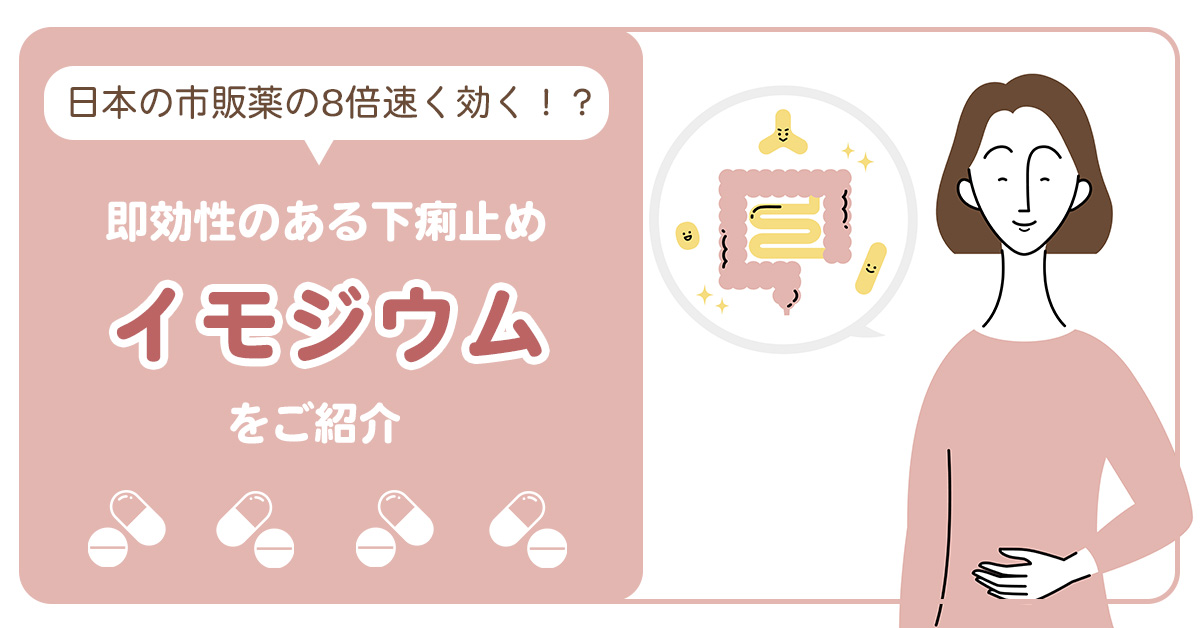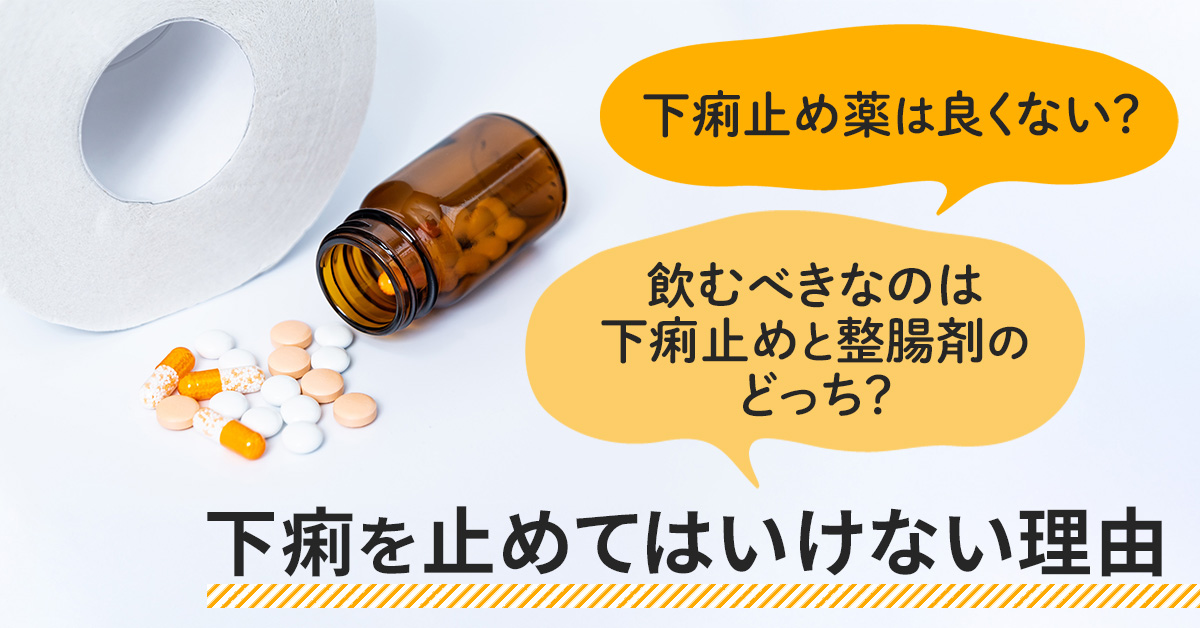下痢止め薬
- 下痢止め薬の種類と作用機序
-
下痢止め薬は、主に以下の3つのカテゴリーに分類されます。
-
止瀉薬
ロペラミドやビスマス製剤などが止瀉薬に含まれます。
ロペラミドはμオピオイド受容体に作用し、腸管の蠕動運動を抑制します。
また、腸管からの水分吸収を促進し、便の固形化を助けます。
ビスマス製剤は腸管粘膜を保護し、抗菌作用も持っています。 -
整腸薬
乳酸菌製剤や酪酸菌製剤などのプロバイオティクスがこれに該当します。
腸内細菌叢のバランスを整え、有害菌の増殖を抑制します。
また、腸管の免疫機能を強化し、下痢の原因となる病原体に対する防御力を高めます。 -
吸着薬
活性炭やタンニン酸アルブミンなどが含まれており、腸管内の有害物質や毒素を吸着し、その影響を軽減します。
特に食中毒や急性胃腸炎による下痢に効果を発揮します。
-
- 下痢止め薬はどんなときに使うべき?
-
下痢止め薬は、下痢の原因や症状の程度によって使うべき状況が異なります。
-
急性の感染性下痢
通常、対症療法が中心となります。
脱水予防のための経口補水液と、必要に応じて整腸薬や吸着薬が使われます。
抗生物質は、特定の細菌性下痢や重症例を除いて通常は使いません。 -
慢性下痢
原因疾患の治療が重要です。
過敏性腸症候群や炎症性腸疾患に伴う下痢には、症状に応じて止瀉薬や整腸薬が用いられます。 -
薬剤性下痢
抗生物質関連下痢には、プロバイオティクスが有効です。 -
外出中の下痢
予防的にビスマス製剤やプロバイオティクスを使用することがあります。
発症時には、ロペラミドなどの止瀉薬が症状緩和に役立ちます。 -
小児の下痢
脱水予防が最も重要です。
ORS(経口補水液)の使用が基本となります。
止瀉薬の使用は慎重に行う必要があり、2歳未満では一般的に使いません。 -
高齢者の下痢
脱水や電解質異常のリスクが高いため、早期の対応が重要です。
薬剤相互作用に注意しながら、適切な下痢止め薬を服用します。 -
免疫不全患者の下痢
症例によっては抗生物質や抗ウイルス薬の使用が必要となります。
-
- 市販の下痢止め薬
-
通勤電車の中や、学校・職場などでお腹が痛くなったときに活躍するのが下痢止め薬です。
緊急時用に、いつも持ち歩いている鞄の中に入れておくと安心です。市販の下痢止め薬には、以下のような薬があります。
- ストッパ下痢止めEX
- ビオフェルミン下痢止め
- 本草正露丸糖衣
- エクトール赤玉
- 下痢止め錠「クニヒロ」
- イヅミ正露丸
下痢が酷い場合には、単に症状を抑えるだけでなく、脱水予防や原因疾患の治療、さらには腸内環境の改善まで視野に入れた治療を視野に入れるべきです。
根本の原因を治療することを目指しましょう。